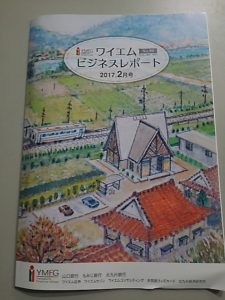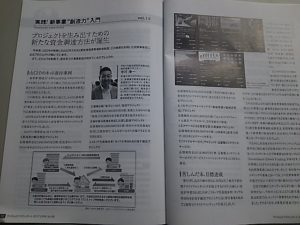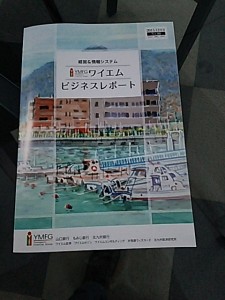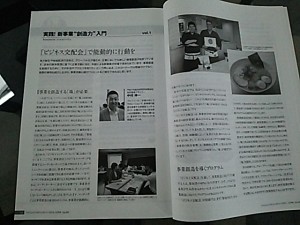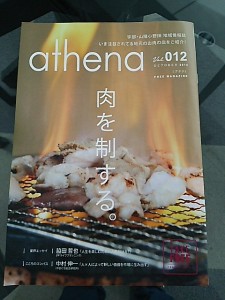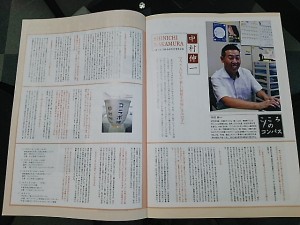2月 28th, 2017 yamasoken
2015年12月からワイエムコンサルティングの機関誌ワイエムビジネスレポートに連載してきました、「実践!新事業”創造力”入門」が2017年2月をもちまして終了することとなりました。
ご購読いただいた皆様、ありがとうございました。
トータル14回の連載となり、毎月原稿を書く作業は事業の棚卸し、そして内容の構成を考えていく上でとても良い経験となりました。
実のところ書籍出版を意識しながら執筆していきましたが、改めて文章を書くことの難しさも再認識しました。
以前、山口商工会議所の月報にて2年間執筆しましたが、文字数も2倍となり、また違った難しさがありましたが、この時と違って編集者がおられたので、とても助かりました。
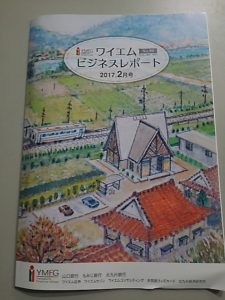
この連載では、事業創造をテーマにして書き始め、それに伴って
事業デザイナーという名称を使うようになり、事業コラボ、地方創生に取り組む中で、生まれた事業などの実例も掲載させていただきました。
実践!新事業”創造力”入門は一区切りつきました。
2017年からの活動は、まさにローカルイノベーションの創出。
山口県だけなく、地域の資源を資産にブラッシュアップして、地方から新たな事業を生み出し、また地方・地域を繋げることで、新たな市場開拓支援を行っていきます。
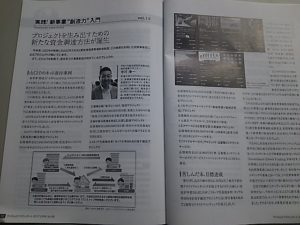
今後も応援、よろしくお願いします。
Posted in 中村伸一所長のコラム, 執筆の紹介
12月 3rd, 2015 yamasoken
このたび、株式会社山口フィナンシャルグループで中国地方唯一の銀行系総合コンサルティング企業、ワイエムコンサルティング株式会社が発行している情報誌「ワイエムビジネスレポート」にて、12月より執筆連載がスタートしました。
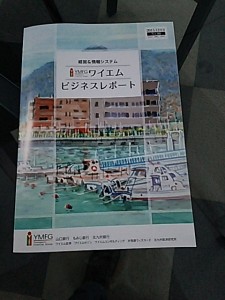
「実践!新事業”創造力”入門」 business creativity
が、タイトルです。
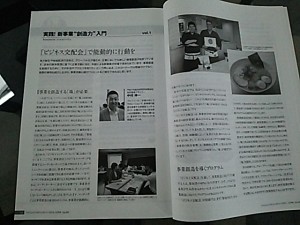
第1回目は、地方からイノベーションを起こすビジネスマッチングの取り組みとして注目されている「ビジネス交配会」について執筆しました。
ビジネス交配会から多くの成果が生まれ、地域経済を活性化させています。
このビジネス交配会から生まれた事例も紹介しています。
今回は、 山口宇部経済新聞主催で開催された「宇部ビジネス交配会」から事業が生まれた 三代目yutakaさんを取り上げました。
ワイエムコンサルティング会員向けの情報誌ですが、
もし手元にあれば、是非、ご覧ください。
地方創生の取り組みのヒントを今後も執筆していきます。

Posted in お知らせ, コラボレーションを創発する支援, 執筆の紹介
10月 14th, 2015 yamasoken
「人×人によって新しい価値を市場に生み出す」
会社勤めを辞めた19年前からこれまで、この想いで仕事をしてきました。
時には失敗もありましたが、時代の変化に合わせて実現は出来ていると思います。
先月、宇部市で発刊されているフリーマガジン「アテナ」さんから取材を受けました。編集者は、19年前まで会社勤めをしていた時の同僚で、気が許せる分、思う存分話すことができました。
取材って、他人の力を借りて自分のことを棚卸しができる、非常に良い機会ですね。取材を受けながら、改めて気づいた自分自身のこと。
本来やりたかった事など、どんどん棚卸しができました。
編集者の友人に感謝です。
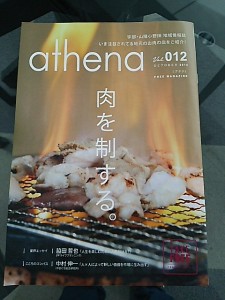
なぜ僕がコラボレーションを活用した事業を行っているのか
が、まとめられているので、読んでいただければと思います。
コラボ、コラボって言い続けていますが、これは僕=コラボを定着させる
ブランディングを意識した行動なのですが、だいぶ定着してきました。
反面、営業や販促の講師をすると、コラボだけでなく営業や販促のことも詳しいですね。とも言われます。本来は、こちらが主とした仕事ではありますが、、、
コラボを意識する前までは、借脳(能)という言葉を使っていました。
人×人で借脳して事業を生み出していこう!!
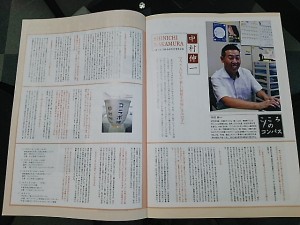
僕の周りでコラボする事業者が急増しています。
これからもコラボ、コラボと、言い続けていきますので、
是非、ワクワクなそしてハッピーなコラボを起こしましょう!!
そして、気づいたこと、僕の仕事ってフリーランスの域だな。
Posted in お知らせ, 執筆の紹介
9月 30th, 2009 yamasoken
事業者が商号(会社やお店の名前)を商標登録するケースが増えてきました。
この背景には、平成18年5月1日に新会社法が施行され、類似商号規制が廃止されたこにより、自社の商号を他人に使われたくないということがあります。
創業支援を行う中でも、創業者の商号に対する熱い思いがあり、創業準備段階で商号の商標登録申請を行い、コーポレートブランド(製品やサービスのブランドではなく、企業名そのものに対するブランドのこと。)として積極的な営業展開を考えるケースも見受けます。
創業時にコーポレートブランドに取り組んだ方とそうでない方を比べると、事業に対する意気込みが全然違う事を創業支援の中で感じます。コーポレートブランドを構築したいという意識が、事業計画の中でも明確にあらわれ、創業者の事業に対する本気度が伝わってきますし、マーケティング計画にも具体的な内容が盛り込まれます。
また、経営者から、「自社をもっと発展させたい、社員の仕事に対する意識を向上させたい」という声をお聞きします。
会社名をブランド化する、自社商品をブランド化するという行動意識を社員全員が持てば、会社全体の意識改革ができるのではないだろうかと、ブランド化に関心をよせる経営者もいるようです。ただ、ブランドとして商標登録をするだけでは、経営を長期的なビジョンでみた場合に、物足りなさがあります。
このブランド化をきっかけとして、会社全体の経営を見直す事が大切です。事業者が行う経営の見直しを経営革新として、商工会議所でも取り組んでいますが、事業者が経営革新に取り組むには、何かきっかけが必要になるではないでしょうか。
ブランド化に向けたポジティブな経営革新こそが将来の自社の強さを生み出すものだと思います。
それでは、ブランドについて説明しましょう。
ブランドは、お客様に自社商品とその他の商品を差別化させて商品を識別させる印と、考えてください。ブランド化に取り組むメリットとしては、
1.購買単価があがる
2.生活者の購買への抵抗感が下がる
3.安定した売上が期待できる
4.プロモーションコストが軽減される。
5.競合に対して優位に立てる。
ことがあります。
また、ブランド化に取り組むにあたって考えないといけない事に、短期間では、ブランド作りは難しく、中長期での取り組みが必要になること。プロモーション活動においては、ビジネスベースでの協力者の確保が必要でもあり、先ほどの中長期の取り組みにかかる時間もコストと換算すれば、ブランド化に向けた投資コストが発生することを考えなければいけません。
ブランド化への取り組みを企業におけるブランド戦略(ブランディング)と呼ばれています。
執筆: 山口商工会議所中小企業支援センター窓口専門家 中村伸一
山口商工会議所月報 2008年8月号
Posted in 執筆の紹介
8月 8th, 2009 yamasoken
日本の中小企業のIT化が遅れていると言われていますが、ホームページに関しては、山口県内でも開設する企業が増えています。
山口県内の企業がホームページを開設し始めたのが今から14年前の1994年頃でした。
主に会社概要(会社の所在地や取り扱い商品やサービス)を掲載するホームページが大半で、取り敢えずホームページを持ってみようという感覚での開設でした。
きらら博が開催された2001年には、ホームページを利用して商品販売を行う事業者が急増します。また、大学生の就職活動がインターネットの利用に移り始め、大学生向けの求人情報を公開するためにホームページを所有する企業も増えました。山口県内の企業がホームページを所有する増加率は、この頃が一番ピークでした。ところが2004年になると、ITの勝ち組負け組だと世間を賑わすようになり、ホームページでの取組みが失敗した事業者から発せられる「ホームページを持っても意味が無い」という風評が拡がり、山口県でも中小企業のホームページに対する投資が激減しました。
しかし2006年後半から、ホームページに投資する企業や開設を検討する企業が増え始めます。この要因としては、ホームページで売上げを伸ばす企業が身近に出てきたことや、安価で便利なITツール(Web通販システムやホームページ自動作成システム)が普及し始めた事にあります。
ホームページを開設する企業の最近の動向としては、事業者自身がホームページで何を行うかを研究し、目的を明確にしていることがあげられます。取り敢えずホームページを持つという感覚から、IT戦略、Web戦略、インターネット・マーケティングという認識でとらえ、経営に組み込むスタイルに変わってきたことにあります。
ある製造小売店では、インターネット・マーケティングでの取組みに成功し、ホームページでの販売が順調に伸び、店舗での販売を縮小し、インターネットや電話からの予約注文で販売していくスタイルに変わりました。ホームページを持つ事でのIT化によって、経営の根幹まで変わるという経営革新が起きた事例です。
逆に、インターネット・マーケティングが上手く行き、ホームページからの注文が殺到したものの自社の体制が整っていなかったばかりに、ホームページでの販売をやめなければいけなくなった事業者もあります。ホームページでの売上げを考えるだけでなく、商品の受注体制、製造体制、出荷体制も考えておく必要があります。
10年前にホームページを開設したままの状態の事業者、5年前にホームページでの通信販売に取組んだけれども、成果が出ずに辞めた事業者もあるかと思います。最近では、ITもICT(Information and Communication Technology)と言い替えられ、知識やデータといった情報を適切に他者(社員や顧客、ビジネスパートナー等)に伝達する為の技術という概念に変わりました。事業者の皆様、最近のIT動向を踏まえ、事業経営へのIT化もといICT化について再度考えてみられてはいかがでしょうか。
執筆: 山口商工会議所中小企業支援センター窓口専門家 中村伸一
山口商工会議所月報 2008年6月号
Posted in 執筆の紹介
5月 9th, 2009 yamasoken
事業計画書が売上げや利益を生むわけではありませんし、時間も掛かるからと計画書を作成する事業者は少ないようです。
最初に事業計画書を作成する場面は、創業の時でしょう。創業時に金融機関から融資を受ける為、創業計画書(事業計画書)を作成した経験を持つ方も多いのではないでしょうか。
創業計画書は、創業者の事業に対する思いをこの計画書に落とし込んで創業者自身で作成することになります。創業計画書に組み込むものとしては、創業動機、創業理念、企業概要、資金調達計画、損益計画、販売計画等があります。
以前、フランチャイズに加盟して創業を考える方からの相談がありました。計画書としては申し分なく、販売手法から広告手法まで細かく計画された素晴らしい創業計画書です。しかしながら、相談者に計画書の内容から質問を出しても本人からの回答がほとんどありません。事業を行う本人の姿がこの創業計画書から見えてきません。実はこの創業計画書、フランチャイズ元が作成した事業計画書をご自分の創業計画書として持参されたものでした。この計画書には本人の事業への思いや姿勢が入ってないものでした。これでは、創業計画書になりません。創業後の相談者の事を考えると本人以上に私が不安になりました。
創業後、年月が経過すると社員の登用や会社の体制などを検討するようになります。そろそろ経営計画書を検討する時期になります。「御社の経営計画書は」と尋ねると、「創業時に作成した計画書」と答える経営者が多くいます。経営を指導する際に、事業内容や考えを早く把握するために、経営計画書の提示を求めますが、大半の企業は提示がありません。見せたくないというより、持ってないというのが現状です。経営計画書に盛り込む内容は、経営理念、経営方針、中・長期事業構想、当期経営目標、当期個別計画、当期数値目標等から成り立ちます。故に経営の羅針盤といわれ、社員に対しての道標にもなります。
経営計画書は作成時点で、事業経過による経験・知識の蓄積があり、事業分析データも収集することが可能であることから、具体的で実行力のある計画書を作成することになります。今から経営計画書を作成するのであれば、「中小企業新事業促進法」の「経営革新支援」の利用も検討するといいでしょう。中小企業新事業促進法は、政府がやる気のある企業を何とか応援しょうというものです。事業計画は、経営革新計画として「何か新しいこと」を取り入れ、その結果も出すことも条件にいれて作成します。この事業計画書を県知事が承認すると、政府系金融機関や都道府県から低金利で融資が受けられる、信用保証の特例が受けられる、都道府県から補助される補助金を受けられる等のメリットがあります。但し、計画の承認は支援措置を保障するものではないので、計画の承認後、利用を希望する支援策の実施機関の審査が必要となります。
経営革新計画のみならず経営計画書、創業計画書の作成方法が分からない方が多いのも事実です。各商工会議所では、相談窓口を設置して専門家による計画書作成の指導を実施していますので、利用されてはいかがでしょうか。
執筆: 山口商工会議所中小企業支援センター窓口専門家 中村伸一
山口商工会議所月報 2008年4月号
Posted in 執筆の紹介