9月 4th, 2012 yamasoken
山口市産業コーディネーターとしての起業支援を終え、商工会議所の起業塾塾長や窓口相談員を継続する中、
2008年から山口県から外に出ての活動に重点を置く事にしました。
起業支援についても山口県外ではどのような事をしているのか情報収集や起業セミナーにも参加してみました。
ちょうどソーシャルビジネスが話題になったりと、これまでの起業支援の方向性を見直すべきではないかと考え始めたのもこの頃です。
これまでの起業がベンチャーを目指せみたいな、起業=上昇志向だったと思います。しかしライフスタイルやライフワークに志向を持った起業が増えてきていると
肌で感じてもいました。
ブログでの情報発信、SNSでのコミュニティづくりなど、仲間とともに楽しむ起業も目にするようになりました。
そして、2010年からfacebookの活用が一般的に始まりコミュニティが多く生まれるようになりました。
起業においてもソーシャルメディアの活用も必用になってきたと実感したのが2011年春でした。
そこで、起業においてもソーシャルメディアの活用も必用だと起業セミナーでの啓蒙を始めました。
特にfacebookの活用を促していますが、その理由の一つが自分ブランディングに使えるからです。
自分ブランディングには、まずは自分自身の棚卸が大切。これは起業する際に私が指導する事といっしょ。
棚卸したものをfacebookの基本情報に記載する事で面白いことが多々おきます。
自分自身の棚卸でいえば、棚卸したものは自分の知的資産になります。
現在、私が力を注いでいるものに知的資産マネジメントというものがあります。
起業前から知的資産の重要性に気づいて、知的資産マネジメントも実行してもらいたいと考えています。
起業後は、知的資産を蓄積していく、そして知的資産を効果的に活用する。
PDCAを繰り返して行くとで、企業価値を事業価値を高めていただきたいと思っています。
9年前に私が起業支援を行った時は、ソーシャルメディアもありませんでしたし、知的資産マネジメントもまだ普及させるまでには至ってませんでした。
この2つの分野を起業支援にまず組み込むことがこれからの起業支援活動には必要で、組み込む事で起業支援の手法にも化学変化が起きると思っています。
10年目を迎える私自身の起業支援は、大きく変化します。
私の周りの方々からの情報や行動を見てみると、現在段階で私が想定している以上の事が起業支援でも始まるのではないかと思います。
今、「起業する為の心得とヒント」のバージョンアップに取り掛かっています。
これからの起業についても書き加えて行ってますので、お楽しみに。
また、このブログにおいても私の起業支援として進行状況を紹介していこうと思います。
山口市産業コーディネーターとしての起業支援を終え、商工会議所の起業塾塾長や窓口相談員を継続する中、
2008年から山口県から外に出ての活動に重点を置く事にしました。
起業支援についても山口県外ではどのような事をしているのか情報収集や起業セミナーにも参加してみました。 ちょうどソーシャルビジネスが話題になったりと、これまでの起業支援の方向性を見直すべきではないかと考え始めたのもこの頃です。
これまでの起業は、ベンチャーを目指せみたいな、起業=上昇志向だったと思います。しかしライフスタイルやライフワークに目を向けた起業家が増えてきていると肌で感じていました。 またブログでの情報発信、SNSでのコミュニティづくりなど、仲間とともに楽しむ起業も目にするようになりました。 そして、2010年からfacebookの活用が一般的に始まり、コミュニティが多く生まれるようになりました。
起業においてもソーシャルメディアの活用が必用になってきたと実感したのが2011年春でした。 そこで、起業においてもソーシャルメディアの活用も必用だと起業セミナーでのソーシャルメディアの啓蒙を始めました。 特にfacebookの活用を促していますが、その理由の一つが自分ブランディングに使えるからです。
自分ブランディングには、まずは自分自身の棚卸が大切。これは起業する際に私が指導する事といっしょ。 棚卸したものをfacebookの基本情報に記載する事で面白いことが多々おきます。 自分自身の棚卸でいえば、棚卸したものは自分の知的資産になります。 現在、私が力を注いでいるものに知的資産マネジメントというものがあります。
起業前から知的資産の重要性に気づいて、知的資産マネジメントも実行してもらいたいと考えています。
起業後は、知的資産を蓄積していく、そして知的資産を効果的に活用する。
PDCAを繰り返して行くとで、企業価値を事業価値を高めていただきたいと思っています。 9年前に私が起業支援を行った時は、ソーシャルメディアもありませんでしたし、知的資産マネジメントもまだ普及させるまでには至ってませんでした。
この2つの分野を起業支援にまず組み込むことがこれからの起業支援活動には必要で、組み込む事で起業支援の手法にも化学変化が起きると思っています。
10年目を迎える私自身の起業支援は、大きく変化します。
私が想定している以上の事が起業支援でも始まるのではないかと思います。 今、「起業する為の心得とヒント」のバージョンアップに取り掛かっています。 これからの起業についても書き加えて行ってますので、お楽しみに。 また、このブログにおいても私の起業支援として
進行状況を紹介していこうと思います。
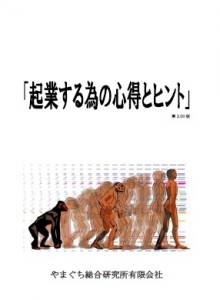 。
。
Posted in 起業支援
9月 2nd, 2012 yamasoken
ここまで「起業帖」や「起業する為の心得とヒント」を作成するプロセスを書いてきました。
今回は、起業支援に携わった中で上手く起業して経営している方の共通点は何だろかと思い、まとめてみました。
起業して上手くいく共通点 11です。
1.起業前に自分自身の棚卸をびっしりしているヒト
2.想いが明確なヒト
3.事業計画表以上の計画書を作成しているヒト
4.見込み客をリスト化しているヒト
5.他人と会う機会を持っているヒト
6.自己表現ができるヒト
7.行動てきるヒト
8.経理がわかるヒト
9.悩むこともできるヒト
10.仲間づくりが上手なヒト
11.最後に借能借脳できるヒト
窓口相談員をやる中で対応すると、起業の意思を持っていても大半の相談者は創業・事業計画書を作ってません。
そこで、創業・事業計画書の必要性を説明して書き方を説明します。
しかしながら、大変の方はここで終わり。再度、相談に来られる方は少ないですね。
逆に継続して相談される方は、創業されています。
創業相談での意気込みと創業準備で大きな違いが出てきます。
ある事業者は、相談に来られた際には、A4で40ページ近い創業計画書を持って来られました。
読むのは大変ですが、でも想いや計画が伝わります。
最初は5~6ページの創業計画だったのが、継続してのアドバイスをしていく事で、創業計画が30ページになった方もおられます。
起業塾では、最初からびっしりと創業計画づくりに入るので起業塾終了時には20ページを越える創業計画になっています。
創業計画で記載する事項を書いていけば、やっぱり20ページにはなります。
この自分が創業する想いをアウトプットする事が大切。
言葉で伝えることも大切ですが、ヒトに見せることも大切。なので、創業計画書はやっぱり必要になります。
それでは、創業計画は枚数によって評価されるのか?
以前、相談対応でこのような創業計画を持ってこられた方があります。
早期退社で起業をしようと、あるFC(フランチャイズ)に加盟して創業を検討された方。
かなり分厚い創業計画書を持参されました。
創業計画書の中身は立派です。特に数字の組み立ては。
この創業計画に基づいて質問をするわけですが、回答はしどろもどろ。数字に関しては根拠になるとしどろもどろ。
そうなんですFC元が創業計画書を作成しているのです。
これじゃーダメですね。
と、やさしく対応しましたが、再訪問はありませんでした。
創業計画は自分で考えて作らないといけませんね。
創業する際には、仲間がいるかどうかがとても重要だと思っています。
創業すると一人になりがち、創業前の仲間は心強いですよ。
そして借能借脳できるヒトをみつけておきましょう。
全てが自分できることはありません。他人の能力を借りる事も大切です。
ここまで「起業帖」や「起業する為の心得とヒント」を作成するプロセスを書いてきました。
今回は、起業支援に携わった中で上手く起業して経営している方の共通点は何だろかと思い、まとめてみました。
起業して上手くいく共通点 11です。
1.起業前に自分自身の棚卸をびっしりしているヒト
2.想いが明確なヒト
3.事業計画表以上の計画書を作成しているヒト
4.見込み客をリスト化しているヒト
5.他人と会う機会を持っているヒト
6.自己表現ができるヒト
7.行動てきるヒト
8.経理がわかるヒト
9.悩むこともできるヒト
10.仲間づくりが上手なヒト
11.最後に借能借脳できるヒト
窓口相談員をやる中で対応すると、起業の意思を持っていても大半の相談者は創業・事業計画書を作ってません。 そこで、創業・事業計画書の必要性を説明して書き方を説明します。 しかしながら、大半の方はここで終わり。再度、相談に来られる方は少ないですね。 逆に継続して相談される方は、創業されています。
創業相談での意気込みと創業準備で大きな違いが出てきます。 ある事業者は、相談に来られた際には、A4で40ページ近い創業計画書を持って来られました。 読むのは大変ですが、でも想いや計画が伝わります。 最初は5~6ページの創業計画だったのが、継続してのアドバイスをしていく事で、創業計画が30ページになった方もおられます。
起業塾では、最初からびっしりと創業計画づくりに入るので起業塾終了時には20ページを越える創業計画になっています。 創業計画で記載する事項を書いていけば、やっぱり20ページにはなります。 この自分が創業する想いをアウトプットする事が大切。
言葉で伝えることも大切ですが、ヒトに見せることも大切。なので、創業計画書はやっぱり必要になります。 それでは、創業計画は枚数によって評価されるのか? 以前、相談対応でこのような創業計画を持ってこられた方があります。 早期退社で起業をしようと、あるFC(フランチャイズ)に加盟して創業を検討された方。 かなり分厚い創業計画書を持参されました。
創業計画書の中身は立派です。特に数字の組み立ては。 この創業計画に基づいて質問をするわけですが、回答はしどろもどろ。数字に関しては根拠になるとしどろもどろ。 そうなんですFC元が創業計画書を作成しているのです。 これじゃーダメですね。
と、やさしく対応しましたが、再訪問はありませんでした。 創業計画は自分で考えて作らないといけませんね。
創業する際には、仲間がいるかどうかがとても重要だと思っています。 創業すると一人になりがち、創業前の仲間は心強いですよ。 そして借能借脳できるヒトをみつけておきましょう。
全てが自分できることはありません。他人の能力を借りる事も大切です。

Posted in 起業支援
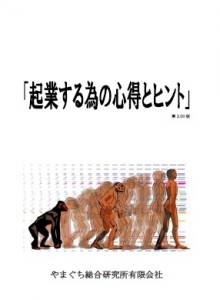 。
。