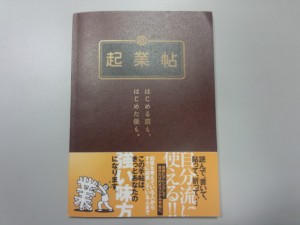8月 30th, 2012 yamasoken
山口市産業コーディネーターに就任して3年経った頃、宇部商工会議所が主催する宇部起業塾での塾長をつとめることになりました。
起業塾には基本的な流れがあって、この流れを軸にカリキュラムを作成しますが、少しだけ自分のオリジナルなコンテンツを入れます。
私は、起業を目指す人達には起業家仲間を作ってもらいたいという思いがありましたので、カリキュラムの中に「連携する、コラボレーションを生み出す」
ためのプログラムを作成して組み込みました。
塾生にはとても評判が良くて、起業塾開催中も開催後も塾生同士が仲良くなれたのはこのプログラムがあったからだと思います。
よかったよっかた。
このプログラムは、起業塾の合間合間にコラボを生み出すワークショップとして実施したわけです。
(当時は、私オリジナルな手法で実施していましたが、1年後にアクティブラーニング社の羽根拓也氏と出会い、自己PR手法を学べた事から、今は2つを合わせたプログラムで
を運用しています。)
この「連携する、コラボレーションを生み出す」のプログラムによって、起業塾終了後に起業塾OB同士でのたくさんのコラボが生まれています。
これも私の目指す起業支援の成果だったわけです。
起業塾塾長となり、起業塾の基本となるものはあったとはいえ、起業塾のプログラム作成は苦労しましたね。
1年目は、とにかく作成したプログラムを運用しながら様子を見ては改善。
2年目は1年目で得た事をベースにかなりボリュームのあるプログラムにしました。
しかしながらボリュームがありすぎて、塾生も大変だったと思います。
3年目は、ボリュームのありすぎたプログラムをシンプルにしていき、ようやく満足のできるプログラムが完成しました。
またこの頃、山口大学経済学部より新事業創造論の非常勤講師のオファーをいただき、非常勤講師として教壇に立つことになりました。
私が起業した時の目標に大学で講師をするというのがありましたので、目標を持つとチャンスって突然きますね。
このチャンスをものにするかがとても重要です。
ただ、訪れたチャンスに気づけばいいのですが、気づか無い人も多いのでは。
目の前を通り過ぎていくこともしばしば。
やっぱりアンテナを立てておくというか、意識しておかないといけないですね。
と、起業の講座ではいつも言っています。
さて、大学の授業の目的は、ビジネスプラン作成の指導とビジネスプランを発表、評価するというものです。
起業塾のプログラムを作成した直後でしたので、このプログラムが新事業創造論でも活用することができました。
大学の授業では座学になりがちになるので、ここでもワークショップを取り入れて、履修者がお互いに学ぶ合うスタイルを作りました。
これもコラボを生み出すプログラムを持っていたので、上手く活用できました。
この授業を受講して大学を卒業してからも私とビジネスとして交流している人もいます。
学生に教えることで、自分自身のスキルアップにもつながります。そして一番良かったのは、若い感覚を学生から学べることですね。
マーケティングや消費者の購買行動を指導する私としては、学生の感性や購買行動を授業を通して学べたのは大きかったです。
起業支援②で紹介した「起業帖」を監修してから2年経ち、今度は「起業の心得とヒント」という小冊子を作成しました。
これは、山口市産業コーディネータでの起業支援ノウハウに起業塾で得たノウハウそして窓口相談員として起業相談に対応した事例をまとめたものです。
既に6回バージョンアップしています。
山口市産業コーディネーターに就任して3年経った頃、宇部商工会議所が主催する宇部起業塾での塾長をつとめることになりました。
起業塾には基本的な流れがあって、この流れを軸にカリキュラムを作成しますが、少しだけ自分のオリジナルなコンテンツを入れます。
私は、起業を目指す人達には起業家仲間を作ってもらいたいという思いがありましたので、カリキュラムの中に「連携する、コラボレーションを生み出す」ためのプログラムを作成して組み込みました。
塾生にはとても評判が良くて、起業塾開催中も開催後も塾生同士が仲良くなれたのはこのプログラムがあったからだと思います。 よかったよかった。
このプログラムは、起業塾の合間合間にコラボを生み出すワークショップとして実施したわけです。 (当時は、私オリジナルな手法で実施していましたが、1年後にアクティブラーニング社の羽根拓也氏と出会い、自己PR手法を学べた事から、今は2つを合わせたプログラムでを運用しています。) この「連携する、コラボレーションを生み出す」のプログラムによって、起業塾終了後に起業塾OB同士でのたくさんのコラボが生まれているわけですが、これも私の目指す起業支援の成果だったわけです。
起業塾塾長となり、起業塾の基本となるものはあったとはいえ、起業塾のプログラム作成は苦労しましたね。 1年目は、作成したプログラムを運用しながら様子を見ては改善。 2年目は1年目で得たノウハウをベースにかなりボリュームのあるプログラムにしました。 しかしながらボリュームがありすぎて、塾生も大変だったと思います。 3年目は、ボリュームのありすぎたプログラムをシンプルにしていき、ようやく満足のできるプログラムが完成しました。
またこの頃、山口大学経済学部より新事業創造論の非常勤講師のオファーをいただき、非常勤講師として教壇に立つことになりました。 私が起業した時の目標に大学で講師をするというのがありましたので、目標を持つとチャンスって突然来ますね。
このチャンスをものにするかがとても重要です。 ただ、訪れたチャンスに気づけばいいのですが、気づか無い人も多いのでは。 目の前を通り過ぎていくこともしばしば。 やっぱりアンテナを立てておくというか、意識しておかないといけないですね。 と、起業の講座ではいつも言っています。
そして自分自身の事を棚卸しておくことも大切です。 大学の授業の目的は、ビジネスプラン作成の指導とビジネスプランを発表、評価するというものです。 起業塾のプログラムを作成した直後でしたので、このプログラムが新事業創造論でも活用することができました。
大学の授業では座学になりがちなので、ここでもワークショップを取り入れて、履修者がお互いに学び合うスタイルを作りました。 これもコラボを生み出すプログラムを持っていたので、効果的に活用できました。 この授業を受講して大学を卒業してからも私とビジネスとして交流している人もいます。 学生に教えることで、自分自身のスキルアップにもつながります。そして一番良かったのは、若い感覚を学生から学べることですね。
マーケティングや消費者の購買行動を指導する私としては、学生の感性や購買行動を授業を通して学べたのは大きかったです。 起業支援②で紹介した「起業帖」を監修してから2年経ち、今度は「起業の心得とヒント」という小冊子を作成しました。 これは、山口市産業コーディネータでの起業支援ノウハウに起業塾で得たノウハウそして窓口相談員として起業相談に対応した事例をまとめたものです。
 既に6回バージョンアップしています。
既に6回バージョンアップしています。
Posted in 起業支援
8月 25th, 2012 yamasoken
私の起業支援は山口市産業コーディネータマネージャーをつとめることになったのが最初というのは前回書きました。
5年半この事業に携わり起業家を生み出してきました。
山口市より起業家が多く生まれてきた理由はここにあります。
山口市には起業家の支援を補助金で行う制度も生まれました。
改善見直しを繰り返しながらも現在も続いています。
起業化支援補助金という制度です。
これは、①事業所開設補助 ②販売促進費補助 ③通信費補助 ④産業財産権出願補助 ⑤法人化申請費補助 ⑥出資受入支援費補助
⑦情報文化拠点地域家賃補助 ⑧ビジネス交流拠点地域家賃補助
といった内容です。
これまでに対象エリアや対象業種、補助額の見直しが実施されてきましたが、起業する方にとっては他市にはあまりない制度です。
この起業化支援補助金が生まれるにあたり、私がアドバイスしています。
私がベンチャー企業の創業に参画した際の経験を元に、もっと起業家が活用できるようにしたのもがこの補助金の内容です。
私がベンチャー企業の創業に参画した時にも、国や県が補助金制度を持っていましたが、ハードルが高くて、到底、創業間もない会社が利用できるものではありませんでした。
準備する資料も複雑で難しい、そして審査も厳しい。
そこで、補助金は少なくてもいいから、起業者向けにはハードルを低くして準備するものを簡素化したものにしようと提案したわけです。
そして、起業家の視点で補助項目を絞り上記のような項目になりました。
実際に利用される方は、①、②、③が多いようでした。
産業コーディネーターに就任してからは、起業化支援補助金制度を利用したい事業者の事業計画作成指導を行ってきました。
創業計画をびっしり作成されている事業者はいいのですが、大半の相談者は、創業計画を作成していません。もちろん作成した経験も持っていません。
ですので、補助金申請の支援をするというよりも創業計画の作成支援してきたわけです。
お蔭で5年間で500件を越える創業計画を見る事ができました。
創業支援をする中で、その方の強み、その企業の強み、その事業の強みを見出すわけですが、これがなかなか面白い訳です。
誰かがそれは、「貴方の強み」ですねと、言わない限りは大半の方は気づきません。
客観的な視点といいましょうか、他人から教わることが多い訳で、産業コーディネーターでの起業支援は、この客観的な立場で指導する事に徹してました。
感情移入すると客観的な発言ができなくなりますからね。
起業家に好評だった山口市産業コーディネータ事業ですが終了する1年前に、起業支援で得たノウハウを本にしようという事になりました。
起業支援のノウハウは私の知的資産ではありますが、山口市産業コーディネーターの設置元である山口市の知的資産でもあります。
今後、山口市で起業を目指す人のために、起業ノウハウを公開するのもやぶさかではありません。
そこで、「起業帖」という山口市発行の冊子が生まれました。
僕も執筆をしていますが、どちらかというと監修という立場でこの冊子の作成に携わりました。
この「起業帖」はとても評判が良くて、多くの市民に行き渡りました。
昨年、県内の商工会議所が起業関係の冊子を発行していますが、この「起業帖」を参考にして作成したというところが多かったようです。
私の起業支援は山口市産業コーディネータマネージャーをつとめることになったのが最初というのは前回書きました。
5年半この事業に携わり起業家を生み出してきました。 山口市より起業家が多く生まれてきた理由はここにあります。
山口市では起業家の支援を補助金で行う制度も生まれました。 改善見直しを繰り返しながらも現在も続いています。 それは起業化支援補助金という制度です。
これは、①事業所開設補助 ②販売促進費補助 ③通信費補助 ④産業財産権出願補助 ⑤法人化申請費補助 ⑥出資受入支援費補助 ⑦情報文化拠点地域家賃補助 ⑧ビジネス交流拠点地域家賃補助 といった内容です。 これまでに対象エリアや対象業種、補助額の見直しが実施されてきました。当時、他市にはあまりない制度でしたので他市の起業準備中の方からも私に相談が来ていました。
この起業化支援補助金が生まれるにあたり、私がアドバイスしています。
私がベンチャー企業の創業に参画した際の経験を元に、もっと起業家が活用できるようにしたものがこの補助金です。 私がベンチャー企業の創業に参画した時にも、国や県が補助金制度を持っていましたが、ハードルが高くて、到底、創業間もない会社が利用できるものではありませんでした。
準備する資料も複雑で難しい、そして審査も厳しい。 そこで、補助金は少なくてもいいから、起業者向けにはハードルを低くして準備するものを簡素化したものにしようと提案したわけです。 そして、起業家の視点で補助項目を絞り上記のような項目になりました。 実際に利用される方は、①、②、③が多いようでした。
産業コーディネーターに就任してからは、起業化支援補助金制度を利用したい事業者の事業計画作成指導を行ってきました。 創業計画をびっしり作成されている事業者はいいのですが、大半の相談者は、創業計画を作成していません。もちろん作成した経験も持っていません。 ですので、補助金申請の支援をするというよりも創業計画の作成支援してきたわけです。
お蔭で5年間で500件を越える創業計画を見る事ができました。 創業支援をする中で、その方の強み、その企業の強み、その事業の強みを見出すわけですが、これがなかなか面白い訳です。 誰かがそれは、「貴方の強み」ですねと、言わない限りは大半の方は気づきません。 客観的な視点といいましょうか、他人から教わることが多い訳で、産業コーディネーターでの起業支援は、この客観的な立場で指導する事に徹してました。
感情移入すると客観的な発言ができなくなりますからね。 起業家に好評だった山口市産業コーディネータ事業ですが、残念ながら5年6ヶ月で終了することになりました。終了の1年前に、起業支援で得たノウハウを本にしようという事になりました。 起業支援のノウハウは私の知的資産ではありますが、山口市産業コーディネーターの設置元である山口市の知的資産でもあります。
今後、山口市で起業を目指す人のために、起業ノウハウを公開するのもやぶさかではありません。 そこで、「起業帖」という山口市発行の冊子が生まれました。 僕も執筆をしていますが、どちらかというと監修という立場でこの冊子の作成に携わりました。 この「起業帖」はとても評判が良くて、多くの感想もいただきました。 昨年、県内の商工会議所が起業関係の冊子を発行していますが、この「起業帖」を参考にして作成したというところが多かったようです。
私が起業支援を始めて5年間の起業ノウハウがここに詰まっています。
Posted in 起業支援
8月 20th, 2012 yamasoken
創業支援の仕事を始めて今年で9年が経過しました。
最初の仕事は、ITベンチャー企業を設立した経験を買われて、山口市の産業コーディネーターに就任したのが創業支援の始まりです。
当時は、ITベンチャー企業のブームもあって、全国的にも創業支援が活発だったんです。
私が就任した山口市産業コーディネーターの主な仕事は、創業相談者の相談対応と創業セミナーの立案と運営、そして創業者に特化したフォーラムの開催でした。
当時はITベンチャー企業の社長をしていて、起業コンサルティングのノウハウもなかったので日々勉強でした。
それでも任についている間に、財団法人 やまぐち産業振興財団のインキュベーションマネージャーや経済産業省管轄の起業支援「ドリームゲート」にて山口県のサポーターをつとめてました。
山口市内で起業する人、山口県外で起業する人、そして様々な業界の起業家と接する事ができて、とても勉強になりました。
この頃は、クリエーター系の起業が多くて面白い人達と知り合えました。
中には上昇志向での起業家もいて、相談対応にも苦慮しました。
起業支援で最初に悟ったのは、教えるのではなくて、相談者の話しを聞く事でした。聞いているうちに相談者が自分で納得するんですよ。
ただ、聞くと言っても何かしら私から問いかけないと相談者からは話されないので、「質問術」も身につきましたね。
そして、起業セミナーでは、相談者からお聞きして事をまとめて私が「起業の心得」として話す流れができました。
私の中では、インプットしたらアウトプットするというバランスのいい仕組みが出来上がりました。
平成19年からは山口商工会議所や宇部商工会議所の窓口相談員や宇部起業塾の塾長をつとめて起業支援のカリキュラムを作成しました。
山口市産業コーディネータの仕事と創業塾や相談窓口での対応から創業相談の件数もトータル2000件は越えたのではないでしょうか。
また関与した創業者も200人は越えていると思います。
結局のところ、創業支援の仕事を始めてからの3年間は創業ノウハウの蓄積と創業事例の蓄積を目指して創業支援の「構築」に取り掛かった事になります。
構築後は見直しを繰り返しながら、創業支援のノウハウを私の知的資産として蓄積しました。
ただ、来年10年目を迎えるにあたって創業支援についても大幅な見直し(変化)をしなければいけないと思っています。
その軸は、創業支援に知的資産マネジメントを組み込む。そして創業塾やセミナーのカリキュラムに知的資産マネジメントを組み込むことで、創業支援に変化をもたらせたい
と考えています。
創業支援の仕事を始めて今年で9年が経過しました。
最初の仕事は、ITベンチャー企業を設立した経験を買われて、山口市の産業コーディネーターに就任したのが創業支援の始まりです。
当時は、ITベンチャー企業のブームもあって、全国的にも創業支援が活発だったんです。
私が就任した山口市産業コーディネーターの主な仕事は、
創業相談者の相談対応と創業セミナーの立案と運営、そして創業者に特化したフォーラムの開催でした。
当時はITベンチャー企業の社長をしていて、起業コンサルティングのノウハウもなかったので日々勉強でした。
そして,その任についている間に、財団法人 やまぐち産業振興財団のインキュベーションマネージャーや経済産業省管轄の起業支援「ドリ ームゲート」にて山口県のサポーターをつとめました。 山口市内で起業する人、山口県外で起業する人、そして様々な業界の起業家と接する事ができて、とても勉強になりました。 この頃は、クリエーター系の起業が多くて面白い人達とも知り合えました。中には上昇志向での起業家もいて、上場に関しての相談対応には苦慮しました。
私自身、経験が無いもので。 起業支援で最初に悟ったのは、教えるのではなくて、相談者の話しを聞く事でした。 聞いているうちに相談者が自分で納得するんですよ。 ただ、聞くと言っても何かしら私から問いかけないと相談者は話されないので、「質問術」も身につきましたね。 起業セミナーでは、相談者からお聞きした事をまとめて、私が「起業の心得」として話す流れができました。
私の中では、インプットしたらアウトプットするというバランスのいい起業支援の仕組みが出来上がったわけです。
平成19年からは山口商工会議所や宇部商工会議所の窓口相談員や宇部起業塾の塾長をつとめて起業支援のカリキュラムを作成しました。 この9年間、山口市産業コーディネータの仕事と創業塾や相談窓口での対応から創業相談の件数もトータル2000件は越えたのではないでしょうか。
また、関与して創業した方も200人は越えていると思います。 結局のところ、創業支援の仕事を始めてからの3年間は創業ノウハウの蓄積と創業事例の蓄積を目指して創業支援の「構築」に取り掛かった事になります。構築後は見直しを繰り返しながら、創業支援のノウハウを私の知的資産として蓄積しました。 ただ来年、10年目を迎える創業支援にあたっては、創業支援手法についても大幅な見直し(変化)をしなければいけないと思っています。 その軸は、創業支援に知的資産マネジメントを組み込む事。 そして創業塾やセミナーのカリキュラムに知的資産マネジメントを組み込むことで、創業支援に変化をもたらせたい。
と、考えています。

Posted in 起業支援
 既に6回バージョンアップしています。
既に6回バージョンアップしています。